「もう誰かに振り回されるのはやめたい」「もっと自分らしく生きたい」──そんな気持ちを抱えている人にこそ、読んでほしい一冊があります。
それが、岸見一郎さんと古賀史健さんの共著『嫌われる勇気』です。この本は、アドラー心理学のエッセンスを対話形式でわかりやすく紹介しながら、私たちが本当に自由で幸福な人生を歩むにはどうしたらいいのかを問いかけてくれます。
出版から10年以上が経った今でも多くの人に読まれ、また多くの人が解説・解釈を発信しているている名著です。アドラー心理学の概念の詳細な解説はほかの方にお任せして、こちらの記事では、この本の「全体を通したメッセージ」と、心に残った個人的に大切な言葉を紹介していきます。
今回の参考書籍
『嫌われる勇気』が伝えるメッセージ|「いま、ここ」にある「自分」
過去も未来もなく、あるのは「いま、ここ」のみ
本文中で第一章(第一夜)から最後まで、表現を変えつつ何度も出てくるメッセージが「過去も未来もなく、あるのは「いま、ここ」のみだから、「いま、ここ」を真剣に生きろ」です。
我々は過去の環境や経験から現在の状況を理解し、未来の想像をします。しかし、実際に生きるのは「いま、ここ」の瞬間のみであり、人生はその瞬間の連続であるとアドラーは考えます。
遠い将来に目標を設定して、いまはその準備期間だと考えるのではなく、今この瞬間も本番であり、真剣に生きることができれば、それは目標を達成したか否かにかかわらず幸福な人生だということです。
また、アドラー心理学のなかで最も有名な考え方である「他者と自分の課題の分離」も、このメッセージに集約されます。いま自分にできることは何なのかを考えて実行し、自分にはどうすることもできないものは受け入れる。自分の課題に集中するということも、「いま、ここ」を真剣に生きることの重要な要素です。
人生における最大の嘘、それは「いま、ここ」を生きないことです。過去を見て、未来を見て、人生全体にうすらぼんやりとした光を当てて、なにか見えたつもりになることです。
――第五夜「いま、ここ」を真剣に生きる より引用
新たな気づきを与えてくれる2つのポイント
われわれは同じ地平の上を並んで歩いている
「同じ平らな地平に、前を進んでいる人もいれば、その後ろを進んでいる人もいる。」
――第二夜 すべての悩みは人間関係 より引用
これは人間関係のとらえ方として、新たな気づきを与えてくれる比喩です。
人には、より優れた存在になろうとする欲求があるとアドラーは考えます。ここで注意しなければならないのは、「他者より」優れた存在ではなく、「今の自分より」優れた存在を目指すべきだということです。
他者を押しのけて階段を上るイメージではなく、平らな場所で自分の足を一歩前に踏み出すイメージです。
「われわれは同じ地平の上を並んで歩く。前にいたり、後ろにいたり、向かっている方向もバラバラだが、それぞれが「いまの自分よりも前に進もうとする」仲間である。」
その後に続く「仲間」についての話や、「目標」についての話とあわせて考えると、「スクランブル交差点」のイメージが近いかもしれません。
「特別な存在」でありたい
「多くの子どもたちはまず「特別に良くあろう」とする。それが叶わなかったとき、今度は一転して「特別に悪くあろう」とする。」
「たとえ叱られるというかたちであっても、子どもは親からの注目を得たい。どんなかたちでもいいから「特別な存在」でありたい。」
――第五夜「いま、ここ」を真剣に生きる より引用
ひとつ上でも「より優れた存在になろうとする欲求」について書きましたが、子どもにとってこれは、親や周囲の人からの注目を集める「特別な存在」になりたいという気持ちにつながります。
そこでまず、親の言いつけを守って、社会性をもった振る舞いをし、勉強やスポーツに精を出します。
しかし、それがうまくいかなかった場合、授業中に大声を出したり、非行に走ったりして注目を集めようとします。
どちらも目的は同じで、「現在の「普通の状態」を脱し、「特別な存在」になること」です。
どれだけ叱っても子どもが問題行動をやめないのは、この目的が達成されているからです。
では、どのようなかかわり方をすれば、この欲求を満たしつつ問題行動を収めることができるのか?
様々なかかわり方が考えられますが、本書から読み取れる方法のひとつは、「特別な行動」ではなく「普通の存在」に注目することです。
他者のことを「行為」のレベルではなく、「存在」のレベルで見ていきましょう。他者が「なにをしたか」で判断せず、そこに存在していること、それ自体を喜び、感謝の言葉をかけていくのです。
――第四夜 世界の中心はどこにあるか より引用
本書では、子どもだけでなく他者との関わり合い全般についての文脈で用いられています。
「行為」を褒めるのでも叱るのでもなく、「存在」そのものをありのままに見て、自分が感じた喜びや感謝を伝える。
そうすることで、「自分は誰かの役に立っている」「自分の存在には価値がある」と実感でき、過剰に他者からの注目や承認を求めることはなくなるということです。
まとめ|名著と言われる所以
本書のプロローグでも書いてあるように、アドラー心理学は科学ではなく哲学であるという点が、この本に時代を超えて普遍的な価値を与えています。
アドラーはもともと、精神分析の創始者として有名なフロイトに師事し、そのカウンセリングのなかで自身の考えを発展させていきました。数年後にはフロイトの主張に異を唱えるかたちで袂を分かち、個人心理学を創始しました。
フロイトが人間の本能や無意識など生物学的な点に注目したのに対して、アドラーは人間が社会的な文脈の中で生きているという点に注目し、対人関係へのアプローチを核とした心理学を主張しています。
科学的ではない、都合の良い解釈だという批判もあったようですが、個人差の大きいこころの問題に対して「誰でも、いつでも変わることができる」と主張し、勇気を与えようとしたのがアドラー心理学。現代の我々にもアドラーの思いは届いているのですね。

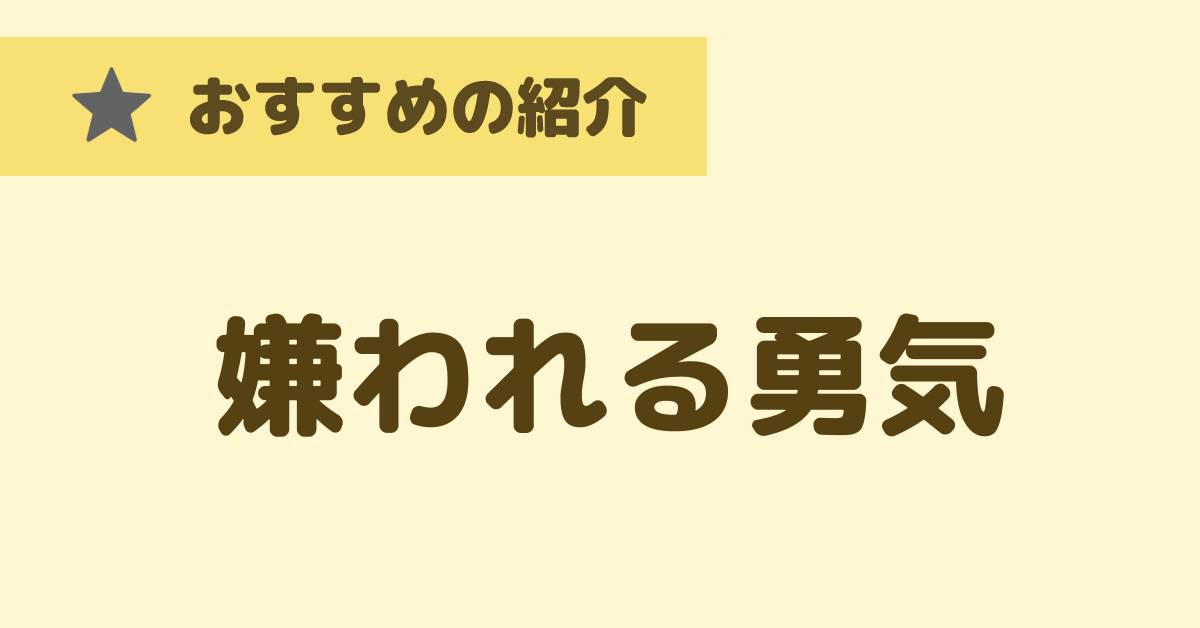
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46dc93b9.d29e6923.46dc93ba.01d19e27/?me_id=1213310&item_id=16720039&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5819%2F9784478025819.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

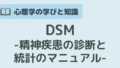
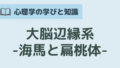
コメント