スポーツや芸術の分野で、日本はアマチュアレベルが非常に高いとよく言われます。全国大会の出場者の技術レベルは世界的にもトップクラス。一方で、海外のように「桁違いの才能」として世界を席巻するプロがなかなか現れないという指摘もあります。
この違いは、単に個人の努力や才能の問題ではなく、文化や教育の歴史的な背景が大きく関係しているのではないでしょうか。
日本の「型」に根ざした学びの文化
日本の部活動は、近代スポーツや芸術であっても、その根底には「武道」に通じる精神があります。武道の学び方は「型」や「形式」を重んじ、まずは形から入ることを重視します。これは、次のような歴史的、地理的、社会的背景から生まれた文化だと考えられます。
- 限られた資源(時間、人材、設備)の中で、より多くの人を初心者から中級者に引き上げ、実践投入できる状態にする必要があった。
- 「型を通じて学ぶ」ことで、効率よく一定水準の技術や精神性を身につけることができた。
- この「型重視」のスタイルが、結果として平均値を引き上げ、全体のレベルを底上げすることにつながった。
つまり、日本は「みんながそこそこできる」社会を築いてきたのです。
「実践投入できる」と「本質を理解している」は別物
ここで注意すべきは、「形式を身につけて実践できる」ことが、必ずしも「本質を理解している」こととは限らないという点です。
- 形式を覚えるだけでは、「楽しむこと」「日常とのつながり」といった創造性や主体性が置き去りにされやすい。
- 中級者から上級者へ成長するには、こうした「本質への気づき」が不可欠になる。
つまり、「教えられたことをこなす」ことはできても、「自分で気づき、創り出す」ことが難しい。これが日本から突出した才能が育ちにくい理由のひとつかもしれません。
欧米文化は「気づき」からの飛躍を重視してきた
一方で、欧州を中心とした海外の歴史はどうだったのでしょうか。
- 古来より、国や文化が支配・交代を繰り返す中で、「ひとつの型を最適化する」という時間が持てなかった。
- そのため、蓄積よりも「革新的な発想」によって、力や成果を伸ばす必要があった。
- こうした環境では、「気づいた者が抜きん出る」「創造性で勝負する」という価値観が育ちやすい。
つまり、「才能」とは、生まれ持ったセンスというより、「気づきと創造の力」なのかもしれません。
資源環境の違いと教育思想への影響
この違いは、資源のあり方にも表れています。
- 物的、人的資源が少ない日本では、「ひとりで何でもできる」ことが求められ、それに適した教育スタイル(型重視・効率重視)が形成された。
- 資源が豊富な欧州では、「適材適所」が可能で、個々の資質を活かすスタイルが育ちやすかった。
この構造が今でも、教育や人材育成の思想に色濃く影響を与えているのです。
まとめ:「突出する才能」を育てるには?
日本は、集団全体のレベルを引き上げるのが非常に得意な社会です。しかし、誰かが飛び抜けることに対しては、無意識のうちにブレーキがかかってしまう構造があるのかもしれません。
もし日本で「突出した才能」を育てたいのならば、「型」から脱却する勇気と、「気づき」や「楽しみ」を育てる環境づくりが必要なのかもしれません。
賛成、反対問わずコメントで意見を頂けたら嬉しいです。

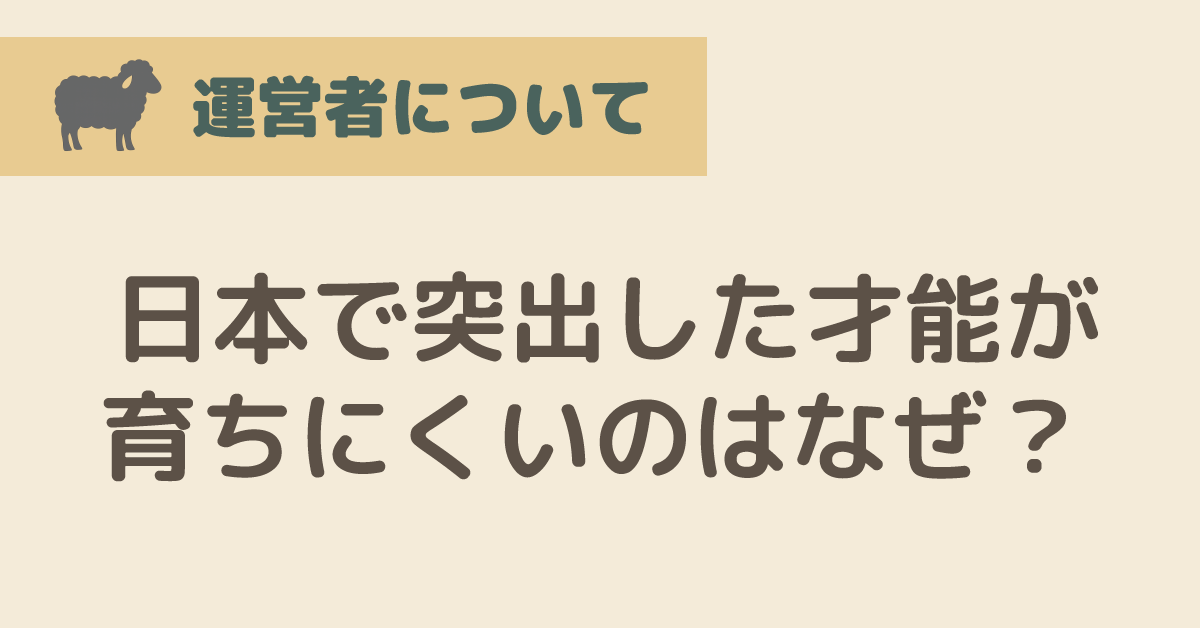
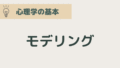
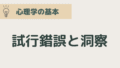
コメント